大和ことほぎの会を主宰する矢加部幸彦先生(古神道修道士・神道音楽家・セラピスト・矢加部オフィス代表)とのご縁をいただき、お話し会に参加しました。
今回のテーマは、『今更聞けない巫女の話 遊女・芸能・巫女』です。
神道について本格的に学ぶのは初めてだったので、とてもワクワクしながら臨みました。
芸能と神事の関係
巫女とは、神の子として「神子(かんこ)」と称される存在。 神と人の間に立ち、神と人とをつなぐ役割を果たす「神ながらの祈り人」です。
「芸道即神道」という歌、舞、 楽 などの芸道はそのまま神道になります。日々の生活全てが神道という教えです。
古来では歌や舞は日常を超越した「非日常」の世界。 本来、楽器を奏でる人は「マレビト」とされ、楽を奏でること自体が神聖な行為とされていました。
また神道には、「振動(バイブレーション)」、音による「周波数」という考え方があり、特に「言霊」はその象徴です。神主さんが唱える祝詞には、言葉の響きや振動が持つ力が込められています。 この振動が神と人を結びつける神髄がありそうですね。
「ハレとケ」の概念
日常は「ケの日」、特別な日は「ハレの日」と呼ばれます。 ハレの日には成人式や結婚式などの節目があり、晴れ着を身にまとい、祝い事や祭りが行われます。
一方、日常で氣が滅入ると「ケガレ(気枯れ)」の状態になってしまいます。 そこで、お祭りを通じて氣を陰から陽へと転じさせることで、「天晴れ(あっぱれ)」な状態を取り戻すのです。 この役割を担っていたのが巫女でした。
巫(かんなぎ)の世界
古来より巫(かんなぎ)は、もともと女性が中心の世界。 神と直接交流できるのは女性とされ、後に「男巫(おかんなぎ)」という言葉が生まれました。
また、能や神楽のように楽器や歌を用いた芸能も、神を楽しませるための神事の一環で 「神遊び」としての神楽(かぐら)も、まさに神と人が交流する目的があります。
巫女と遊女
古来、巫女は神と遊ぶ存在であり、「遊女」という言葉の語源にもなっています。 現代では遊女と巫女が別の存在として認識されていますが、時を遡ると、神と一体化する巫女は聖なる存在でした。
琉球王国の女性祭司最高位「聞得大君(きこえおおきみ)」も、神との共寝を儀式とし、霊力を得て国王を守る役目を担っていました。 同様の祭儀は、日本の大嘗祭にも見られます。
猿女一族と遊部(あそびべ)
古代氏族の「猿女一族(遊部)」は、天皇が崩御された際には、遺体を安置する「殯宮(もがりのみや)」において歌や踊りを奉納する神事を行われていました。この氏族は『古事記』や『日本書紀』に登場する天鈿女命(あめのうずめのみこと)を祖とする一族で天鈿女命は、天照大御神が天岩戸に隠れた際、舞を舞って天照を外へ誘い出した女神。
現代では「遊女=売春婦」というイメージがありますが、「春」の音は「ハレ(晴れ)」。 もともと遊女は「晴れ人」として神聖な役割を担っていたのです。 そして菩薩へと昇華するそうです。
ちなみに、2022年に大ヒットしたアニメ映画『すずめの戸締まり』の主人公・岩戸すずめちゃんの名前は、新海誠監督がインスピレーションを得て名付けたそうです。作品には、「行ってきます。扉の向こうには、すべての時間があった。」という印象的な言葉が登場します。
東日本大震災がモチーフとなった作品ですが、絶望の中にあってもそこには、希望の光があること。心の世界で過去・現在・未来と向き合い、氣付く(自分と向き合う)ことだそうです。

巫女の分類
巫女は大きく2つの系統に分類されると言われています。それが「神和系(かんなぎ)」と「口寄せ系」です。
もともと「神子」と呼ばれていた巫女は、神託を受け、それを権力者(主に男性)に伝える役割を担っていました。これが「神和系」とされます。一方、「口寄せ系」は「座下(くらおろし)」とも呼ばれ、精霊などを自身に降ろし(憑依させ)、その存在の代弁者としてメッセージを伝える役割を果たしていました。
琉球王国の「祝女(ノロ)」や「ユタ」とも共通点があります。ノロは王府によって任命され、地域の神事や祭祀を司る存在です。政治的な役割も担っており、国王を霊的に守護する存在として、国王の健康や王国の安泰を祈りました。
一方、ユタは個人の相談役としての役割が強く霊的な力を持つとされ、人々の悩みや病気の治療、先祖供養などを行いました。そしてユタは口寄せの能力を持つことが多く、亡くなった人の霊や精霊と交信することで助言を与える存在です。
こうした信仰のあり方には、シャーマニズムの影響が色濃く残っており、日本本土の巫女と琉球文化の霊的存在が密接に関わっていることが分かります。
今回、巫女・遊女・芸能の歴史を辿ることで、琉球文化との類似点や、日本文化・神道の奥深さを改めて実感する機会となり出逢いに感謝。ありがとうございました。
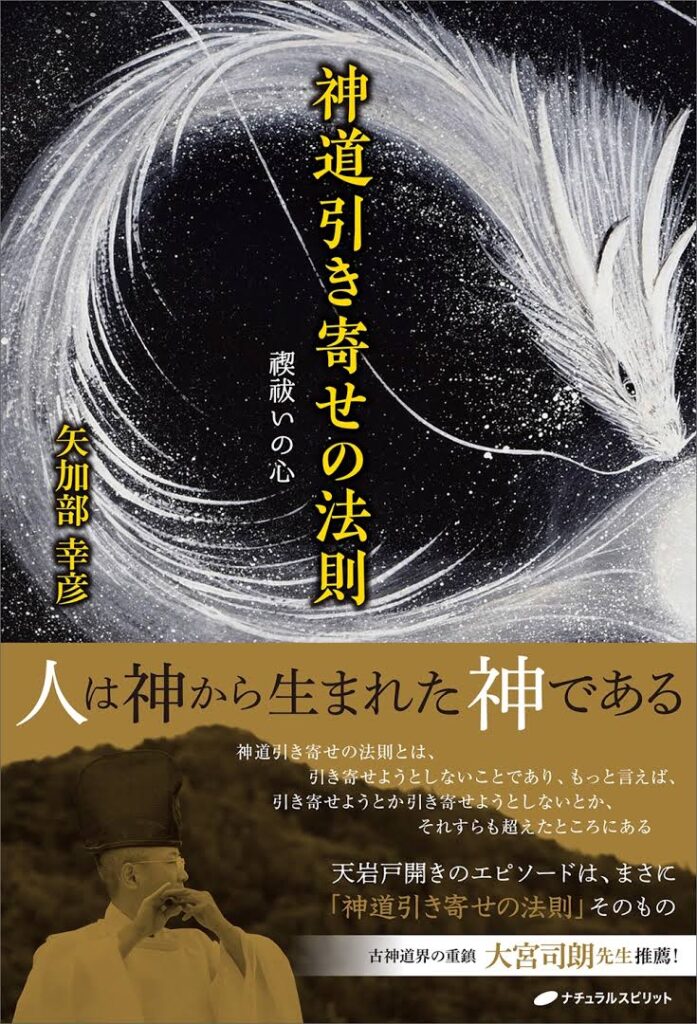




コメント